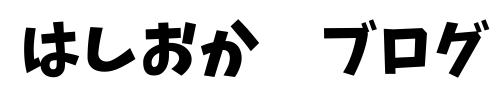学校教育で英語を学習しても話せるようにはならないということは、よく言われます。僕自身も振り返ると、文法などの学習は、英語を使って話すことに自ら大きな壁を作ってしまったように思います。学校の英語教育は、試験のための英語を身につけることが目的なのです。当時、音声の教材にも適切なものは身近ではなく、話し言葉としての英語を聞くことができる環境は今ほど整ってはいませんでした。DJの小林克也さんは、FENを聞いて英語を身につけたと言います。FENを受信できる環境を羨ましく思いました。(受信できたとしても、おそらく米軍の方々のためのラジオ放送のため、ネイティブ英語すぎて何も身につかなかったことでしょう。)
英語には興味があり、大学を卒業してからも英語が話せるようになりたいなぁと学習教材を探していました。幕末の志士たちは、英語学習などしなくてもペリーたちとコミュニケーションしました。明治時代には、ネイティブよりも英作文の上手な日本人もいたそうです。改めて昔の日本人はすごいなぁと誇りに思います。インターネットで使われる言語の7割は英語だと言われます。これから英語は必須だろうと、さしたる目的はありませんでしたが、いろいろな英語学習の教材を本屋で購入し、英語学習を試行錯誤し続けました。
「英会話 絶対音読」國弘正雄[編]シリーズ
この教材に出会えたことが幸運だったと思います。「音読で英語回路を作る」をねらって、学習が組まれています。中学英語の教科書レベルのテキストから学び直しができます。CDがついていて、英語を聞くことができるのも大きな魅力でした。(僕の中学校の時代には、英語教師らしい英語教師は少なく「俺の英語は東北訛りだからなぁ。」なんて平気で言っていました。ネイティブの英語の発音に飢えていました)この本で紹介されている通りのやり方で英語の学習を続けました。いつの間にかテキストを諳んじることができるようになりました。身についてきていることが実感できました。そうすると、入門編から標準編へ、標準編から挑戦編へとステップアップし、学習を続けました。職場でオーストラリアの方と話す機会があり、リップサービスかもしれませんが、「英語の発音が良いね。日本人では珍しいね。」ということを英語で言われ、嬉しくなりました。音読学習の成果です。その後も出会う外国の方と可能な限り話しました。すると、音読で諳んじることができるようになっていたためか、英語が使えるようになっていました。英語回路が確かに出来上がったのだと思います。「自分の英語が通じている。」という感覚とともに大きな自信と喜びにもなりました。外国の方を交えて、飲み会をしたり(お酒が入るとさらに、心が広くなり間違いを気にせず英語を話せるようになるのでオススメです。)、自宅に招いたりしました。子ども達も、恥ずかしがりながらもコミュニケーションをとっていました。その後、娘は外語大学に入り、3年生で休学して、エージェントなどもつけずカナダに渡航し、ワーキングホリデー制度を活用して1年間滞在し貴重な経験を積んだようです。帰国後、電話で英語を使って普通に会話しているのを聞いて、我が子ながらすごいなぁと感心しました。確かめてはいませんが、幼い頃の外国の方との交流もその土台の一部になっているのではないかと僕の心の中で思っています。
英語の音読学習は、本の中に書かれている通りに、毎日続けました。今は、新しい教材にチャレンジはしていませんが、復讐を兼ねて、CD教材をかけ、シャドゥイング(本書の中でも紹介されています。)で英語回路が錆びつかないようにしています。
音読学習は、未知の可能性を秘めている
そう僕は、考えています。英語での音読学習の効能を知りました。この学習法は、応用が利きます。日常会話で活用したい日本語のフレーズや覚えたいこと、身につけたいこと、身につけたい思考様式(マインドセット)さえも、僕は音読を継続することで回路が出来上がると考えています。音読を応用し学習や日常に取り入れると、自分でも自覚しないうちに、大きく変革できる可能性させあると僕は思っています。
音読は、学習法として大きな可能性を秘めています。
ここまで読んでいただきありがとうございます。良い1日になりますように。