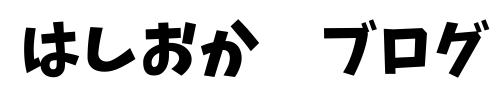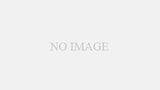学校については、よくマスメディアにも取り上げられます。子どもへの対応だけではなく、困難な保護者への対応もしなければならないことや残業代も休憩時間、休日も取れないこと。本業の授業以外の報告や提出物の多さにより多忙を極めている、休職する先生も多い、先生のなり手がいないなど、教育には、あまり良い報道はないようです。
昭和の頃は、「熱血先生」(だったかなぁ?名前を忘れました。)「3年B組金八先生」「スクールウォーズ」などのドラマで学校が取り上げられていたのを覚えています。(あまりみていませんでしたが。)その頃の風潮としては、子どもと教師が正面から向き合い、ぶつかりながらお互いに人間性を高め合っていく…みたいな内容だったように思います。現代のみなさんが見たら、「昭和って…、こんなだったんだ…。」って驚かれそうです。
育った環境の異なる個性的な子どもたちがいて、同じ数だけ価値観の違う社会経験を積んだ保護者がいて、集団生活を送る学校は大変だろうなと思います。学校に行かなくても今やスマホやPCが教えてくれる。AIの進歩により、文字や文章を書けなくても、計算ができなくても生きていけそうです。そんな中で、変わらない学校教育の価値観に、意味を見出せず、魅力を感じない…だから不登校が急増しているのかなと推測します。そんなとき、教育ってなんだろうって、考えてしまいます。
ドキュメンタリー映画「みんなの学校」を見ました。涙が出てきました。学校の在り方が素晴らしいのです。大阪の公立大空小学校を取り上げた映画です。僕の知る学校、学生時代の学校とは全く別の学校でした。あまりにも別物です。ただ「あぁ、これだ!この学校はきっと今必要とされている学校だ。」と思いました。いろんな個性を持つ子達みんなが安心して生活できているのです。「校長先生の考え方とリーダーシップでここまで変えられるものなのか。」と感動さえしました。
大空小学校の校長先生が書いた著書「「ふつうの子」なんて、どこにもいない」木村泰子(家の光協会)を読みました。木村泰子校長先生は、「机をガタガタさせる子を「周りに迷惑をかける困った子」と見るか、「この子はみんなと一緒にいることに不安を感じて困っている子」と感じるか。」その大人の受け入れ方が大切だと述べています。やはり、考え方・マインドセットが大事なのです。子ども達に、安心感を与えられるかが大事なのでしょう。
仕事上、大人でも平易な言葉で、繰り返し説いて聞かせることが大事だと言われます。立派な目標をお題目として掲げるよりも、日々向き合いながら、大事なことを滔々と語り聞かせることが大事なのでしょう。大空小学校も学校のルールは一つ「人の嫌がることはしない。」のみだそうです。なるほどなぁと思いました。集団で同じ敷地、同じ空間で生活する上でとても大事なことです。そして一つだけ。みんなにとってわかりやすく優しい。
学校の魅力ってなんだろう?友達がいることは、大きな要因としてあげられそうです。逆もありそうですが。学校の意味ってなんだろう?学校の価値ってなんだろう?義務教育の意味はなんだろう?
我が子は大学で何を学んでくるのだろう。今度帰省したときに、何を学んでいるか、どう考えるか、ぜひ聞いてみたいと思います。
今日も、読んでいただきありがとうございます。良い1日になりますように。