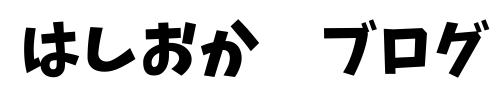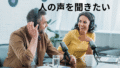教師が、人を思う優しさと深い教育観を持って、予測不能の時代に生きる子どもたちを思い、問いかけて対話を促し、子どもたち自身が学校を作るようにしていく。僕には、現代の魅力的な学校です。子どもたちは、「学校なんてやだ。」「友達とずっと遊んでいたい。」「家でずっとゲームしていたい。」が本音かもしれませんが。学校という同年代の子供たちが集団生活を通して、社会的な人格になってほしいという大人の願いとの妥協点は、先述の学校の姿だろうと思うのです。
自分たちで責任を持って作る魅力的な学校で6〜9年間を過ごした子どもたちは、きっと10年後、20年後の地域を素晴らしいものにしていくだろうなと想像します。まさに、子どもたちの存在は希望そのもので、魅力的な学校で過ごした子どもたちは社会のそして将来の希望でもあります。
子どもたち自身が作り上げていく魅力的な学校で、どんな力が育まれることが理想なのでしょう。
予測不能の世の中で充実した生き方をするためには…、どんな力が必要なのだろう。まだ私には、考えがありませんので、木村泰子先生の考えを引用しながら考えてみたいと思います。
高めたい4つの力
人を大切にする力
多様性社会を生きて働くための基礎となります。蔑まれて嬉しい人はいないでしょう。お互いに人として認め合い、社会の中でともに生きていくことは必要ですね。「人を大切にする」ということは、深い意味を含んでいます。ただただ優しくすることが人を大切にすることではありません。その人がこれから生きていくことを考えると、時に厳しく接することも人を大切にすることになる場合もあるでしょう。
自分の考えを持つ力
すべての学力の源になる「主体性」を育むことにつながります。僕自身は、あまり自己主張が得意ではありませんでした。自分の考えはあっても、多くの考えに迎合していく傾向がありました。僕は少数派の考え方になることが多かったのです。グループや職場では、多数の考えによって方向性やプロジェクトが動き出します。多数による決まるのです。最近は、採用されなくても自分の考えを話すことができるようにしています。採用されなくてもいいのです。グループや職場の考えの視野が少しでも広がることや自分の考えを表明すること、そしてそれに挑戦できたことに価値があると思っています。
自分を表現する力
自分の言葉で「伝える」相手の表現を「聞く」ことは、社会生活を送る上で、大切です。前項でも述べましたが、考えを持っていてもそれをアウトプットしなければ伝わりません。以心伝心という言葉を持つ私たち日本人でも難しいことです。これだけ海外の人と触れ合い、コミュニケーションをする時代、考えているだけでは伝わらない世の中になりました。アウトプットを心がけて、表現していくことが大切です。
チャレンジする力
失敗は「反省」より「やり直し」をしよう。学ぶことと実行すること、これがセットにしていかないと何も変わらない。何事も一歩踏み出すのは、怖いものです。けれど考えているだけでは何も変わりません。実行に移さないと何も変わらないのです。失敗をしたとしても、変わったかどうかで言えば、変えることができたという点で、評価にあたるのではないでしょうか。考えるだけではなく、実行すること。それに必要なのがチャレンジする力ですね。
言ったことや考えていることを認める。否定しない。
話したことや考えていることを馬鹿にされたり、冷やかされたり、否定されたりすると、次に話すことに怖さや嫌悪感を感じるものです。無意識に「僕の考えは、みんなと比べてずれてるんだなぁ。」「あまり良くない考え方なんだなぁ。」「僕は何も言わない方がいいようだなぁ。」などと考えてしまう。幼い頃、特にも小中学生くらいの時には、言ったことや考えていること、子どもの存在をひっくるめて否定せず、認める態度が考えを持ち表現することにつながると改めて思います。
きっとそれは、大空小学校の校長先生をはじめ、先生方は、そのような態度を持っているからこそ、子ども達は安心して落ち着いて良い学校生活を送れるのだろうなぁ、そう思いました。
今日も読んでいただき、ありがとうございます。良い1日になりますように。