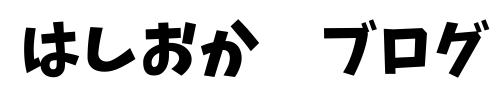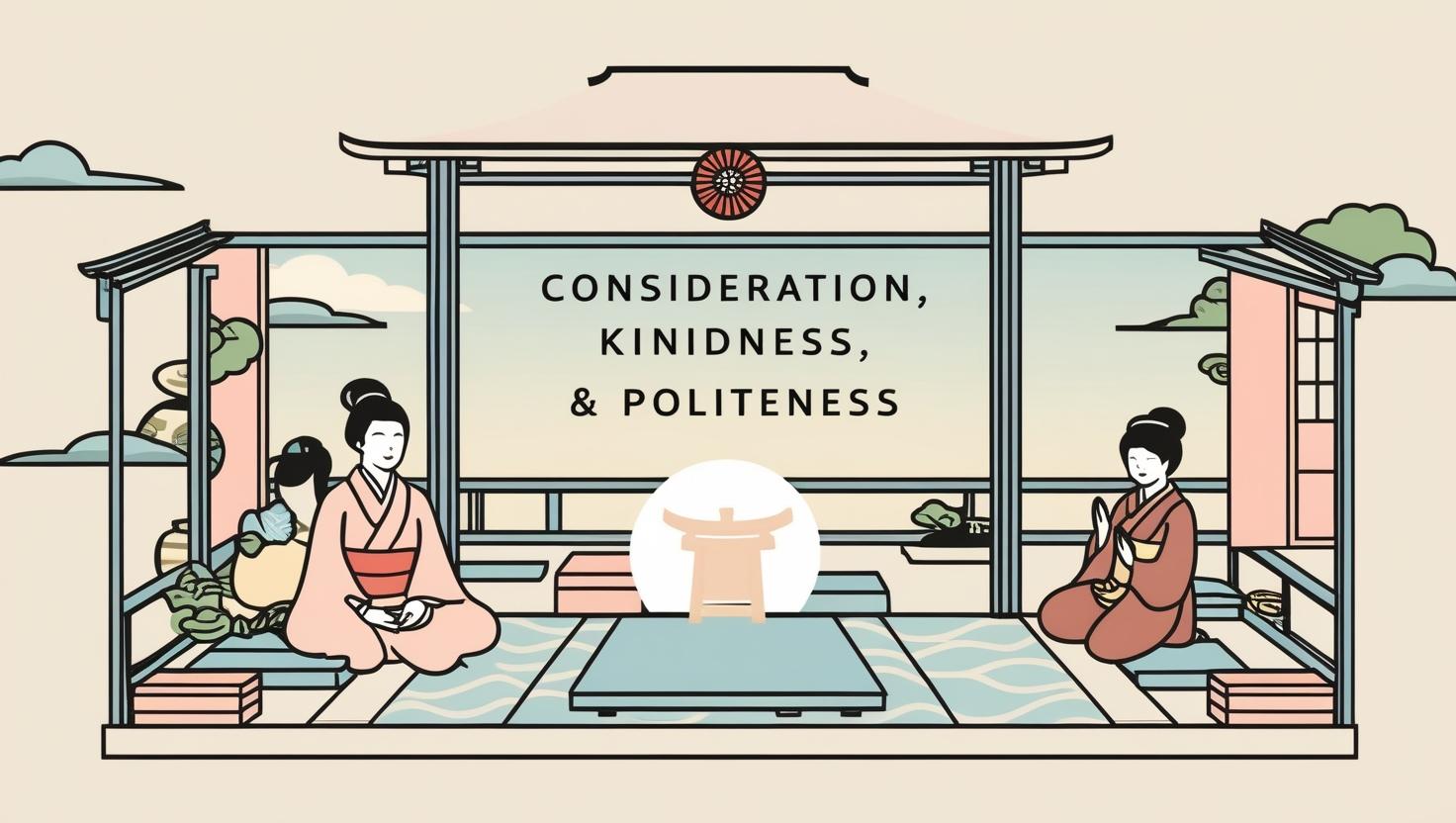自動車を運転しているとイラっして、心がささくれだってしまうことがあります。「こちらが優先車線だろう。なんで無理に入ってくるんだよ。」「なんだ?。ハイビームが眩しいな。気づいていないのか?やり返してやろうか。」「後ろに近づきすぎ。なんか煽ってんの?」みたいなことは頻繁にあります。運転中は、イラッとしやすいとともに、危険を回避するための緊張感を伴いやすいのでしょう。そんな時でも、信号のない横断歩道を渡ろうとしている人がいると自動車は止まらなければなりません。急いでいても、フゥと息を吐いて、きちんと止まります。
歩行者がお辞儀をしてくれる礼儀正しさが作る世の中の雰囲気
歩行者がこちらを気遣い、道路を急いで渡り、横断後にお辞儀をしてくれることが僕の住む地域では、よくあります。特に小中学生。大人でも時折いらっしゃいます。そんな時、自分のささくれ立った心は、癒されます。そして、反省を促されます。
社会のルールで言えば、自動車は止まり、歩行者は胸を張って横断して構わない。けれど、そのルールを当たり前だと横柄な態度になるのではなく、「忙しい中ご苦労様です。世の中のためお仕事をしてくださりありがとうございます。その中でも止まっていただき、すみません。」そんな心配りをこの行為から感じるのです。子どもたちが、このような姿を見せてくれると「まだ世の中大丈夫かな。」とホッとします。気がつくと、ホッと力を抜いて運転することができている。その行為の生み出してくれた気持ちであり、雰囲気です。
相手を気遣う思いやりが世の中を良くしていく
歩道を横断後のお辞儀のように、相手を気遣う思いやりに、癒される人は多いでしょう。世の中は嫌なニュースが読まれやすく広まりやすい。自己中心的で、他人を見下すことで自分の居場所を確保し、優越感に浸っているようなそんなニュースもよく目にします。けれど、多くの日本人は、世の中を良くしようと日々働き、仕事をし、子どもたちを育てています。人々と協働して働くわけなので、思うようにいかないことや他人や他部署との摩擦や軋轢、価値観の違いなど様々なことに苛まれながらも生きています。みんな同じ。きっとこの社会を築いてきた父祖たちもきっと同じ思いで生きてきたことでしょう。
「聖徳太子の存在は、現在確たる証拠がなく、歴史の教科書から削除された」みたいなことを聞きました。僕が小・中学生の頃は聖徳太子は、十七条の憲法や冠位十二階などの律令制度の黎明期の業績の中に、こんな言葉を残したと学んだ記憶があります。
和を以て貴しと為す
「和を以て貴しと為す」十七条の憲法の第1条だそうです。「仲良く協力して、みんなでやっていこう」これが私たちの社会を良いものにしてきた根幹ではないかなぁと考えます。きっとそれ以前から、言葉にならずともそのような風潮があったのでしょう。言葉として残ることで、より一層強く広く私たちに意識づけられてきたに違いありません。
色々な価値観を持つ人も損得だけで考える人も増えてきたと言われます。きっと私たちのコミュニティの中が自分中心になり、相手の立場を思いやる共同体の受け皿からこぼれ落ち、仲良く思いやりを持つことの価値を知らずに生活してしまいやすい世の中になってきたのかもしれません。
「和」を大切に、守っていこう
歩行後のお辞儀のような思いやりや困っている人を見かけたら、自分のことはさておき助けられる優しさ、そんな周りの人たちが持つ「和」に感謝し守っていこう、それはきっと今後の世の中を、子どもたちの住む社会を、住みやすい良い世の中にしていくはずだ。そう思える出来事でした。
ここまで読んでくれてありがとうございます。良い1日でありますように。